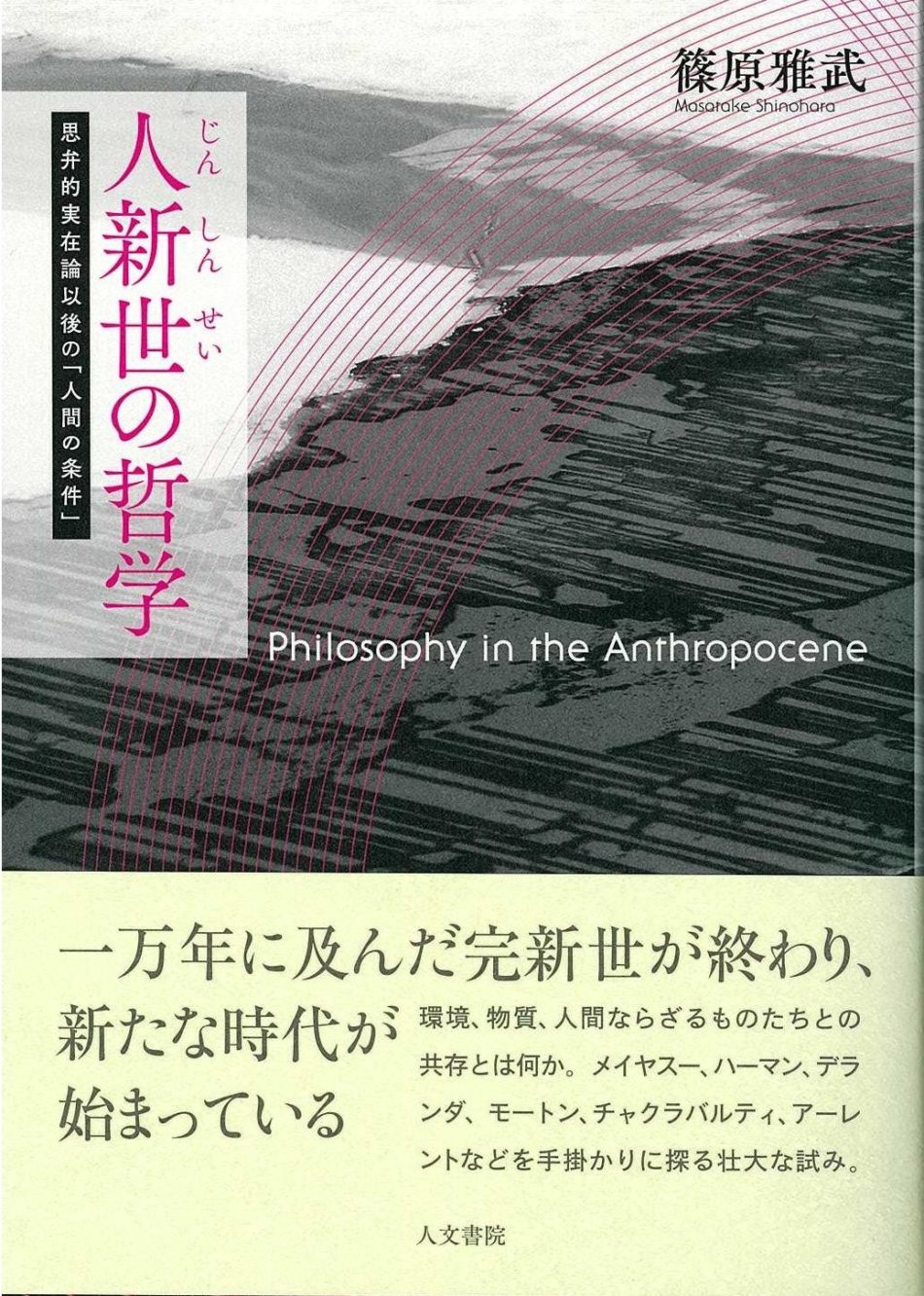せっかくなので今後本を読んだら、半分自分用のメモとして簡単に書き残しておこうと思います。人に読んでもらうようにと思うとかなり時間がかかってしまうので、継続的に続けるためにも、あくまでサラッと書きます。(急いで、重要な要素だけを書いたので、ややぶっきらぼうで不用意な議論になっています。すみません。)
前提としての『人間の条件』
今、授業でアーレントの『人間の条件』を読んでいるのだが、この本は議論の枠組みの設定がとても良い。
アーレントは人間は「条件づけられた存在」であるとしたうえで、人間の基本的な条件となるものを三つ挙げる。一つ目が「人間が生物的過程に縛られた存在であること」、二つ目が「人間が円環的な自然過程とは別に人工物の世界を作ること」、三つ目が「人間が多数の人間の中で生きていること」である。そしてさらに、これらの基本的な条件から人間は人間の世界を物理的にも関係的にも作りあげていくが、そうした自分たちの作った世界にもまた「条件づけられる」とする。つまり人間は、自分たちの作るもの・生み出すものによって自分たちの条件を更新していく存在である。
『人間の条件』は全編を通してこの三項を巡って、それらが歴史の中でどう変奏してきたのかを描くものである。議論の基底として設定された三項は、素朴さ故に射程が広く、かつ相互に捻じれがあるために、現代にも十分通用する議論を可能にしている。(三次元空間のあらゆる位置が三つの基底ベクトルを用いて表せるように、この三項は人間について議論する上での素晴らしい基底を設定してくれていると思う。)
アーレントの議論は、「人間の条件」というのはそれ自体移ろいゆくものであるということを前提としている。簡単にいえば、三つの項目それぞれがある種の欲望を持ったドライバーである。そのうちの一つあるいはいくつかが作動して世界の在り方をひとつ更新する。するとその新しい世界の中で三つのうちまた別のドライバーが作動してさらに世界像を更新する。その中で三項は互いに接近したり相反したりしながら意味付けを変えていく。そういう運動体になっているようなイメージである。
『人間の条件』のやっていることは、そのための基底の設定と、それらの基底に基づく近代までの歴史の解釈、そして、これからに関するささやかな見通しであるように思える。そう思うと、アーレントの議論は時代ごとに更新され、乗り越えられて行かねばならない。それがアーレントにとっても本望なのではないだろうか。アーレントが目指した哲学は「永遠」ではなく、「不死」なのだと僕は勝手に思っている。
人新世というフェーズ
篠原さんのこの本でやろうとしているのは、まさにその「アーレントの乗り越え」という名の更新作業のように思う。
人新世という状況は、まさにこの枠組みの更新を必要とする事態である。
「人新世(anthropocene)」とは、地質学者であるパウル・クルッツェンが2002年に『ネイチャー』に掲載された「人間の地質学」という論文の中で提唱した概念である。簡単にいえば、地質や気候といったそれまではそれ自体自律的であった自然環境が、今や人間の影響を受けて変質する、つまり、地質や気候までも人間の仕業(しわざ)になってしまうというというような時代のことである。それは今日まで一万二千年続いた温暖な時代としての「完新世」に終わりを告げるものであるという。
これは明らかにアーレントが議論したことを超え出る事態である。
なぜならアーレントは、「自然」と「人工物の世界」について次のように考えているからである。(『人新世の哲学』p89あたり参照。)
①「自然」は「人工物の世界」の外部である。瓦礫、雑草からなる意味をなさない世界である。それは意味を成す「人工物の世界」の外にある。
②「自然」は「人工物の世界」の前提(あるいは土台)である。人間は「自然」から材料を得て、「自然」の上に(中に?)「人工物の世界」をつくる。
これは「自然」と「人工物の世界」の①離脱と②接続という二面を表している。
そして、アーレントの上記のような理解の背景には、大きく二つの(やや矛盾した)前提があるように思える。(以下の二つは篠原さんのものをもとにしつつも、私の個人的な解釈を含んでいる。)
・「人工物の世界」は自己完結したものである。
・「自然」は無限の懐を持っている。それは「人工物の世界」に必要な材料を(無限に)供してくれるし、不要になったものを(無限に)受け止めてくれる。(それはアーレントの言うところの「許し」だったのではないかと思う。)
近現代の社会は、自分たちの世界が自己完結したものであるというイメージを強化してきた。そのために、本当はあるはずの自然との「接続点」をなるべく外縁へと追いやることでフレームアウトさせてきた。それでも「自然」が無限の懐でもって、それらの処理を事も無げに受け止め続けることで、我々はその接続点を意識することなく自己完結的な「人工的な世界」を構築することができていると感じているのである。
しかし、人新世の状況が明らかにしたのは「自然の懐は無限ではなかった」ということである。何もかもを定常化させてくれるような不変項として前提・土台となっていた「自然」は、人間の営みに影響を受けて変化してしまっている。
そして、ここで明らかになったもう一つの根本的な姿勢は「人間の作る世界は自己完結したものではなかった」というものである。篠原さんはこれを東日本震災の経験と結びつけて描いている。震災と津波は、我々の世界に急にその外部から割れ目が入れられ、世界が崩れていく経験であった。同様に、地球温暖化やオゾン層破壊などは(そこまでの鮮烈さは持てないものではあるにしろ)、人間の自己完結した世界が外部から脅かされる、前提としていた土台が揺らぐ事態である。
つまり、人新世という状況は、「不変の自然」と「その上に人間が建てる自己完結した世界」というアーレント的な世界観の構図を崩すものである。これは「自然」は「人工物の世界」を条件づけるという一意的・一方向的な関係であったのが、「人工的な世界」がまた「自然」へ作用するという逆方向のベクトルが働き始めたということであり、つまり不動の起点・原点のようなものとしてあった「自然」が動点として浮遊し始めるということである。
そうした、「人間の条件」のための不動の原点の喪失、というのが人新世ではないだろうか。人新世の「人間の条件」はより一層「人間によりつくられたもの」に条件付けられたものへと移行していく。
ただし、それは自己完結した世界を拡大していくということではない。むしろ「自己完結した(と思っていた)世界」の限界性に立ち向かっていかなければならない時代の到来を意味しているのではないか。
新しい認識論へ(エコロジカルな?)
ここで、篠原さんが提示するのは認識論の転回である。
これまでの思弁的・形而上学的な思考法は基本的に人間相互の作用や人間の世界に参入した「意味のある事物」を扱うものであり、ある種の自己完結性を持っていた。そしてそれが、自己完結的な世界像と結びついているという。
それをモートンらの言うようなエコロジカルな認識論へと転回するべきではないかという。エコロジカルな認識論とは簡単にいえば、「意味」を与えられる以前の事物の世界(すなわち「自然」の世界)も含めて感じていこうということである。
ただし、それは「人工物の世界」と「自然」を一致させていくことではない。この辺がとても難しいのだが、線引きはある。ただその線引きがつねに揺らいで、交感の中で絶えず更新され書き換えられていくものである。と認識するのがいいのではないだろうか。何が人間世界にとって有意味なもので、何が無意味なものかが、一意的に決まるのではない。この世に存在するすべての事物が「有意味になり得る」偶有性(コンティンジェンシー)を持っている。その瞬間ごとに、人間の有意味である世界に取り入れられる要素群は変わっていく。それを絶えず更新し続けるために〈外〉の世界を感受し続ける必要があるし、その時々で適切な要素群をアレンジメントするための詩的感性を持ち合わせている必要がある。(なにがアレンジメントに加えられたのかは、事後的にしかわからない。)
言い換えると次の三点になる。①「人工物の世界」=有意味な世界と「自然」=無意味な世界の境界はなくならないが、絶えず揺らぐものである、②あらゆる事物は有意味/無意味の区分の以前に存在し、有意味にもなるし無意味にもなる偶有性を持っている、③何を有意味なものとして取り集めるか(アレンジメントするか)は、詩的感性による。
このように、絶えず〈外〉と交感し続けることで、自己完結性を逃れ、ある種〈外〉の変化の予兆を敏感に感じとって、気を使いながら関係していけるのではないかというのが、このエコロジカルな認識論なのだと思う。
こうした認識論はかなり共感するし自分自身の考えとも近いのだが、これが十分有効な解答なのかは疑わしいと思っている。
エコロジカルな認識論には、いまのところまだ限界性があるように思う。というのは、身体スケールよりもずっと大きなシステムの効果に対してどのように交感していくかということが見えていない。「意味化されず」「物理的にも見えていない」ものをどう認識して立ち向かうか、ということはとても難しい。実際のところ、地球温暖化やオゾン層破壊といった問題は、データで示されて初めて意味として理解できるが、とても事物の次元で感じられるものではない。
やはり、「自然」との接続点はいまだに、システム全体の外縁に配置されており、私たちが日常的にその現場に立ち会うことはほとんどなくなっている。そのうえで、どのようにシステム規模での「自然」=〈外〉との交感をしていくべきなのだろうか。これについては僕はまだ答えを持ち合わせていないし、篠原さんも同様のように見える。エコロジカルな認識論をどこまで拡張しうるのか。今のところ身体や詩的感性(=比喩・連想の構造)に依拠していると思われるエコロジカルな感受性をシステムのレベルに拡張していくための何かが必要なようにおもえるが、まだわからない。集団的な詩的感性のようなものが可能なのか?どうだろう。
ただ、この本を読んで面白かったのは、「人新世」という状況が、どのような問題なのか、どのような問いなのかということを割と明確に設定できたことかなと思っている。「人新世」はアーレントを含め、近代が前提としてきた地球という不動点が動き始めた時代であり、人間が一層人間によって条件づけられる(が自己完結は出来ない)時代である。
※やや個人的な解釈の多めの読解でした。基本的に篠原さんの言わんとすることの延長で書いているつもりですが、何か違う点があればご指摘ください。