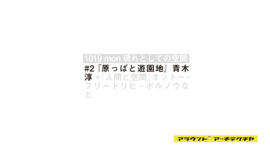ざるドーム、洗濯ばさみ橋
今日は最初にある作品を紹介したいと思います。クワクボリョウタさんの「10番目の感傷(線・点・面)」というインタラクティブアートです。僕もつい最近ある授業で紹介され知ったのですが、思わず見入ってしまいました。
まずは、ご覧ください。(全画面推奨。流し見すると魅力が半減します…!)
この作品はプラレールの線路沿いに置かれた小物や日用品の中を、LEDを乗せた小さな列車が走っていき、影を壁に投影するというものです。そこに登場するのはプラスチックのざるや洗濯ばさみなど身近な小物ですが、それが大きく壁に映し出されたとき、その影は建物や都市のような迫力あるイメージとして私たちに立ち現れます。
作品のタイトルに「感傷」とありますが、車窓を景色が通り過ぎていくように流れていく影はたしかに、どこかセンチメンタルな気分を漂わせています。それは自分の田舎の風景のようでもあり、知らない異国のようでもあり、また記憶の中を旅しているようでもありました。
うっとりと五分間、心地よい郷愁に浸った後、ふとどうしてこの表現が成立しているのか?ということが気になり始めました。というのも、この展示では日用品の影を映し出しただけであって、建物や街並みの再現度で言えば全然「リアル」ではありません。それにも関わらず、この作品で呼び起こされる感情や体験はある種の〈リアリティ〉をもっているのです。(この二つが別物であることを強調する意味で「リアル」と〈リアル〉で使い分けます)
精巧につくられたジオラマの中を走るのであれば、話は簡単です。一言「リアルだったなぁ」といえばそれで十分でしょう。しかし、この作品では洗濯ばさみもざるも隠されてはおらず、それの影を見ているのだと分かるようになっています。言ってしまえばこの作品では、実体として「リアル」であろうとすることからむしろ遠ざかっているように見えます。
それにも関わらず、この迫ってくるような心象の〈リアリティ〉は何なのでしょうか。
ときわ荘の復元
ところで、この真逆の体験がつい最近ありました。
私の住んでいる東長崎・椎名町のエリアはかつて文化人の住む下町としてとても栄えており、特に手塚治虫、赤塚不二夫、藤子不二雄などの名だたる漫画家が住んでいたという「ときわ荘」が有名です。漫画家たちが住んでいたころの白黒写真を見たことがありますが、独特の遊民感と緊張感のある廊下が印象的でした。
その「ときわ荘」はいまはもう取り壊されているのですが、なんと最近その建物を豊島区とファンで共同出資して「ときわ荘ミュージアム」として完全再現するということになりました。着々と工事も進み、この4月にオープンするということになったのです。地元の商店街にも「ときわ荘ミュージアム」の垂れ幕が並びました。
結局、コロナの影響でオープンは延期になったのですが、先日散歩をしていた時思いがけずその建物を見つけました。
さすが「忠実に再現」しているだけあって、佇まいや古びた雰囲気がものすごく「リアル」に表現されていました。(とはいえ元の建物の佇まいは知らなかったのですが。)ちゃんと記録をもとに汚れ方までエイジング加工で再現していたようで、なかなかすごいなぁと思いました。
しかし、特に心に迫ってくるものがなかった。外観しか見てませんが、そこに何も感じることができなかった。僕が漫画に詳しくときわ荘についてもっと知っていればまた違ったのかもしれませんが、少なくともその建物自体が醸す、モノとしての〈リアリティ〉はちっとも感じられなかったのでした。(それよりも、その後調べているときに知った、これを建設するにあたっての寄付金の424,390,543円という額面の方が何か圧倒的なものを感じました。)
ただし、もしかするとここでいうような〈リアリティ〉の不在は新築では仕方ないのかもしれません。今後時間を重ねていけば「ときわ荘ミュージアム」もそれなりの空気感を帯びてくることもあるのかもしれません。
リアリティとアクチュアリティ
そんなことを考えていて、ちょうどピッタリのエッセイを思い出しました。
建築家の中山英之さんが去年ギャラリー間で行っていた展示のパンフレットにあった「ふたつの『リアル』」というタイトルの短いエッセイです。そのエッセイは冒頭にこんな風に書かれています。
映画の感想にしばしば言われる「リアル」という言葉がうまく使えません。「リアルな映画」と言ったとき、この言葉にふたつの意味が混ざっている感じがして、それが座りを悪くさせているのだと思います。「ジュラシックパーク」の恐竜も「リアル」、ジュリエッタ・マッシーナの演技も「リアル」、どうもしっくりきません。(108)
『建築のそれからにまつわる五本の映画』中山英之
これは、まさに今考えていたことです。そして、文章はこう続きます。
たぶん、混ざっているのは「再現性」と「現実性」なのかな、と思います。そう友人に話したら、恐竜の方は「リアリティ」でいいけれど、もうひとつのモヤモヤした方は「アクチュアリティ」って言えばいいんだよ、と教えてくれました。なるほど。(108)
『建築のそれからにまつわる五本の映画』中山英之
この二つのリアルを使い分けてみると、さっきの話も腑に落ちるような気がしてきます。
以下では中山さんの語法にならって、先ほどまで「リアル」と書いていた方をそのまま「リアル」、〈リアル〉と〈〉で括っていた方を「アクチュアル」と呼ぶことにしましょう。つまり、ときわ荘ミュージアムは「リアル」だけど「アクチュアル」でないということです。
中山さんは「リアリティ」は再現性と「アクチュアリティ」は現実性と対応していると言います。
「アクチュアリティ」について、現実性という表現がやや分かりづらいですが、私としては「真に迫ってくる感じ」、あるいはもっとカジュアルに言うなら「心にすっとフィットする感じ」と理解しています。映画でも小説でも建物でも音楽でも、思わず心を奪われてのめり込んでしまうような作品に出会うことがありますが、そういう時に心に浸入してくる何かが「アクチュアリティ」なのでしょう。(とはいえ、大事な概念なのでここでわかり切った気にならず、今後も考えていくことにします。)
この分類で言うと、冒頭の映像作品「10番目の感傷(線・点・面)」は「リアル」ではないけれど「アクチュアル」な作品だった。他方、ときわ荘ミュージアムは「リアル」だけれど、「アクチュアル」でない建物だった。どうして「リアリティ」とかけ離れたところに「アクチュアリティ」が生まれ、逆に「リアリティ」を追い求めても「アクチュアリティ」が生じないのでしょう。
中山さんはこの捻じれについても言及していて、面白い指摘があります。
中山さんはウェス・アンダーソン監督の「ライフ・アクアティック」という映画について、「全編にわたって、台本、演出、装置、すべてがつくりものであることをこれでもかと白状し続ける映画」と評し、次のように言うのです。
つまり、「映画の方が徹底してリアリティからの距離を示し続けてくれるおかげで、初めて生まれるアクチュアリティ」といった感じでしょうか。(中略)それはたぶん、ヒッチコック監督も知っていた、映画そのものの中からしか出てこない、現実を超えた現実のようなものです。(112)
『建築のそれからにまつわる五本の映画』中山英之
これはとても示唆に富んでいるなと思います。「リアリティからの距離を示すこと」がむしろ「アクチュアリティ」に対しては誠実であることもあるということです。思い返せば、冒頭の「10番目の感傷(点・線・面)」でも、洗濯バサミやザルが少しも悪びれることなく露わになっていました。素性の知れた日用品をつかい、しかもそれを敢えて見せることが「リアリティからの距離を示すこと」になり、結果として「アクチュアリティ」に繋がったのではないでしょうか。
次ページへつづく