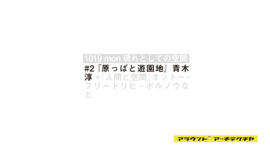要約
空間には、「あらかじめそこで行われることがわかっている建築(「遊園地」)とそこで行われることでその中身がつくられていく建築(「原っぱ」)の二種類」がある。
「遊園地」的な建築は、建築家の「意図」の中にその人の振舞いや情操を規定し尽くしてしまう。それに対して、「原っぱ」的な空間は「いつでもこの空間を別のあり方に変えることができる」という感覚を与えるものであり、そこにおいてこそ人は真に自由になれる。
アレグザンダーは、「要求される複雑な諸条件」(=コンテクスト)を処理する能力がデザイナーにはない、という指摘を通じて、人間による構築の限界点をあぶり出そうとした。対して、青木はもし仮に「要求される複雑な諸条件」を処理できたとして、それは意図の中に人を拘束する点で「遊園地」的なものの域を出ないという。そして、「要求される複雑な諸条件」が有限で不変なものである(が故にそこから導かれる形も有限の要素に対応した不変のものである)というアレグザンダーの前提に異議を申し立てる。
「原っぱ」的な建築は、その後作り変え可能な余白をつくることや曖昧につくることではない。むしろ、現場の要求とは無関係につくられた幾何的ルールに基づいて建築をつくり、その空間が極力人の行為や情操に対して、「意図」を持たないようにつくることである、という。(それは「原っぱ」の草が生えてくるように、人の感覚とは切り離された「自然」的な作り方である)
それにより、空間の質(弱い規定力)と人々の行為が対等になり、空間とそこに住む人が感じあい作用しあうような成熟した関係が作られるのである。
※弱い規定力、という言葉は、文中で青木さんは使っていないが、「遊園地」的な建築の規定力が強い、という論旨があったため勝手に造語して用いた。
ある廃校での展示会について
『原っぱと遊園地』でははじめに、美術展の会場として使われた廃校の小学校が登場します。そして、そこではそれぞれのアーティストに元教室や給食室などだった部屋が一つ与えられ、アーティストは部屋に応じて作品を制作し展示します。
給食室には、数個の窯が床に据えられたまま、部屋の真ん中に行儀良く並んでいた。たとえば、そんな部屋が、中川絵梨に与えられている。壁に無数のステンレスのを張って、その上に筆を走らせる。部屋が最初からもっていた質は変わらない。そこになにかを上書きすることで、給食室という意味は消える。意味をもたない質だけが、ひそかに増長する。(6)
不思議なことに廃校の小学校での展示は、美術館での展示よりも空間と調和し、作品の良さが際立ったものであったといいます。青木さんはその理由を以下のように考察しています。
どうして小学校としてつくられた建物のほうがいい美術館になってしまうのか。
理由のひとつは、作家と空間の関係にあると思う。牛込原町小学校では、多くの作家は与えられた空間にとても敏感である。その空間を前提にした展示を工夫している。……与えられた空間がもっているなにかが残される。その上でその空間が別物に変容させられている。
つまり、ここでは作品の多くが、それが設置される空間との関係の中で成立しているのである。もちろん、これは美術にとって、しごく当然のことだ。だけれども、その間にいい関係が生まれるためには、与えらえる空間が主導しすぎても、脇役にまわりすぎても駄目なのだ。どちらが主導するというのではなく、対等でなくてはならないのだ。そして、それは難しいことなのである。(8)
つまり小学校の展示では、空間が一方的に展示を決定づけるのでも、また、アーティストが一方的に展示を構成してしまうのでもなく、空間の示す質をアーティストが汲み取りながら新たな意味付けを与えたからこそ、両者が調和した空間が生まれていたというのである。
そして、青木さんはどうして廃校になった小学校が「程よい規定力」を持つことが出来たのかを考察し、その小学校が機能主義の産物であったからこそだと指摘します。機能主義の建築は、人間がそこでどのように感じ、どのように振舞うかということに関して程よく無頓着です。だからこそ、空間の規定力が強すぎず、そこで人が自由に読みかえることを許容したのだといいます。
一方の牛込原町小学校は、単純な論理でつくられた、狭隘な敷地の都市部に建てられている、かつてどこにでもあった建物である。校庭を囲んで、コの字型に建てられた三階建ての片廊下。敷地の形状と、方位と、採光条件と、求められた教室の大きさと数と、質素な予算と、法規制に対する最適解として割り出されただけの小学校である。(9)
とはいえ、小学校が小学校として使われているうちは、やはり空間の規定とそこで行われる行為の目的が一致してしまうので、なかなかズレは生じてきません。空間の規定力が人間の行為と対等になるのは、元の意味付けが剥げ落ちたときだといいます。空間の規定力と人間の行為が対等になると、人間が自分の暮らし方や使い方に応じて空間を規定しかえすことが出来ます。それこそが、自分の環境を自分次第で変えられる自由の感覚に結びついているのだといいます。
でも、機能主義建築の残念なところは、それが想定された使われ方で実際に使われてしまうところだ。そうなってしまうと、そこでの行為はやっぱり拘束される。 (10)
しかし、いつしか、その学校が廃校になり、子供たちが消え、荷物が片付けられ、貼り紙が剥がされ、什器備品が運び出される。すると、その自然性、つまり、人にどうそれを感じさせようとしたかという視点をもたない、明快な決定ルールの遂行が際立ってくる。……ぼくには、この瞬間が、人間にとって最良の環境なのではないか、と思われるのである。そういうところではじめて、人間はなにか自分の力でその環境を変えられる、つまりそれに拮抗できると感じるのではないか、と思うのである。大きくいえば、ぼくは、建築とは、自分を取り巻く環境は自分次第である、そういう感覚のために行う行為だと考えている。(10f)
二つの空間タイプ:「原っぱ」と「遊園地」
そして、青木さんは「程よい規定力」の状態となった建築を「原っぱ」に例えます。原っぱには草が生い茂っていたり、凸凹があったりと予め何らかの条件が与えられています。しかし、子供たちがそこで遊ぶとき、そうした先行条件は遊びのための格好のキッカケとなるのです。たとえば、こっちの木は僕らの陣地で、あの土のところにいるときはタッチされてもセーフで…というように。しかしこれらのルールは空間によって一方的に規定されたものではありません。空間や形態はほんのきっかけを与えただけです。
また逆に、「更地」でもいけないと云います。「更地」とは空間による規定力がゼロの状態です。真っ平で何の特徴もない更地からは遊び方が生まれてこないでしょう。「程よい規定力」とは、そこでのふるまいを規定しないまでも、ふるまいのためのキッカケを与えてくれるようなもののことです。
ともかく、廃校になった機能主義的小学校の空間は、ちょうど原っぱのように、人間にそれに対するかかわり方の自由を与える。原っぱとは、つまり空き地である。宅地が造成され区画される。これは人工的な営みである。塀が築かれ、土地の形がきちんと確定される。一度は土地が均され、雑草が刈り取られる。そこまで行って、なにかの理由で、放置される。時間が経過して、セイタカアワダチソウなどの雑草が、背丈ほどに伸びてくる。そして、原っぱができ上がる。更地というだけでは原っぱではない。放置後の、適切な度合いの自然の遂行を必要とする。(11)
原っぱとは、宅地として完成する一歩手前で、その意図が見えなくなってしまった空間である。(中略)原っぱという、確かにつくられた空間がそのつくられた意図を失っている環境を体現している物はなかったからである。(11f)
「原っぱ」に見られるような住む人と空間の間の対等関係(16)
そして、「原っぱ」の対極にあるもう一つの空間タイプとして、「遊園地」を登場させます。「遊園地」では遊び方があらかじめ決められ、与えられています。そこでの人間の行為や、あるいはそこでの情操(どのように感じるか)までも、予め計画し、制御されているのです。そこにおいて人間は、一見自由に楽しんでいるようでありながら、既定の演出の枠内にいるのです。
ちょっと雑な気がするけれど、建築は、遊園地と原っぱの二種類のジャンルに分類できるのではないか、と思う。あらかじめそこで行われることがわかっている建築(「遊園地」)とそこで行われることでその中身がつくられていく建築(「原っぱ」)の二種類である。(14)
原っぱの楽しみは、その場所での遊び方を発明する楽しみであり、そこで今日何が起きることになるのか、あらかじめ分からないことの楽しみだった。
それが、人間の空間に対するかかわり方の自由ということの意味だ。この自由は、別の意味で同じくらい楽しかった遊園地と対極にある。遊園地は演出されている。(12)
かつての標準的小学校は、空間だけを取り出してみれば、ほとんど原っぱと同じ質をもっていた。後の小学校によくあるような、ぼくにはなぜそんなことが必要なのかがまるで理解できない、教室の境を曖昧にし、子供たちのいろいろな精神的要求に対応して、あらかじめいろいろな場所を用意してあげようとしてつくられた、押しつけがましく、人の心にまで土足であがり込むような小学校のつくり方とは対極にある空間である。後者の小学校の質は遊園地に近い。一見自由に思えても、その自由は見えない檻のなかの自由だ。(13)
牛込原町小学校がどうして「美術館」として優れていたのか。それは、美術館という空間が、人間が自分の力でなにかをつくっていくということに捧げられた空間であるからであり、とすれば、つくる人のそことのかかわり方があらかじめ規定されたものではなくて、そことのかかわり方の自由が望まれるからだ、とぼくは思う。廃校になった牛込原町小学校は、原っぱと同じく、人間の感覚とは一度は切れた決定ルールによって生成し、しかしその決定ルールが根拠を失った空間だったのである。そうして、偶然にそこで人がつくることと、与えらえる空間の規定力の対等が実現されていたのである。(13)
次ページへ続く